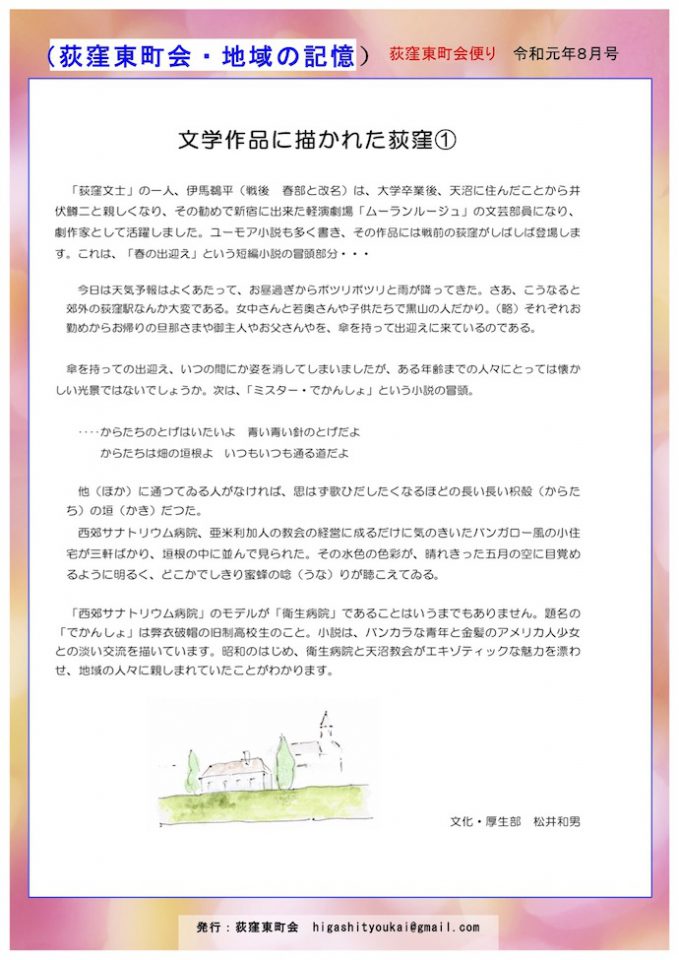
文学作品に描かれた荻窪①
「荻窪文士」の一人、伊馬鵜平(戦後 春部と改名)は、大学卒業後、天沼に住んだことから井伏鱒二と親しくなり、その勧めで新宿に出来た軽音楽劇場「ムーランルージュ」の文芸部員になり、劇作家として活躍しました。ユーモア小説も多く書き、その作品には戦前の荻窪がしばしば登場します。これは「春の出迎え」という短編小説の冒頭部分・・・
今日は天気予報はよくあたって、お昼過ぎからポツリポツリと雨が降ってきた。さあ、こうなると郊外の荻窪駅なんか大変である。女中さんと若奥さんや子供たちで黒山の人だかり、(略)それぞれお勤めからお帰りの旦那さまや御主人やお父さんやを、傘を持って出迎えに来ているのである。
傘を持っての出迎え、いつの間にか姿を消してしまいましたが、ある年齢までの人々にとっては懐かしい光景ではないでしょうか。次は、「ミスター・でかんしょ」という小説の冒頭。
・・・からたちのとげはいたいよ 青い青い針のとげだよ
からたちは畑の垣根よ いつもいつも通る道だよ
他(ほか)に通ってゐる人がなければ、思わず歌いだしたくなるほどの長い長い枳殻(からたち)の垣(かき)だった。
西郊ナトリウム病院、亜米利加人の教会の経営になるだけに気の利いたバンガロー風の小住宅が三軒ばかり、垣根の中に並んで見られた。その水色の色彩が、晴れきった五月の空に目覚めるように明るく、どこかでしきりに蜂蜜の唸(うな)りが聞こえてゐる。
「西郊ナトリウム病院」のモデルが「衛生病院」であることはいうまでもありません。題名の「でかんしょ」は弊衣破帽の旧制高校生のこと、小説は、バンカラな青年と金髪のアメリカ人少女の淡い交流を描いています。昭和のはじめ、衛生病院と天沼教会がエキゾティックな魅力を漂わせ、地域の人々に親しまれていたことがわかります。
文化厚生部 松井和男
